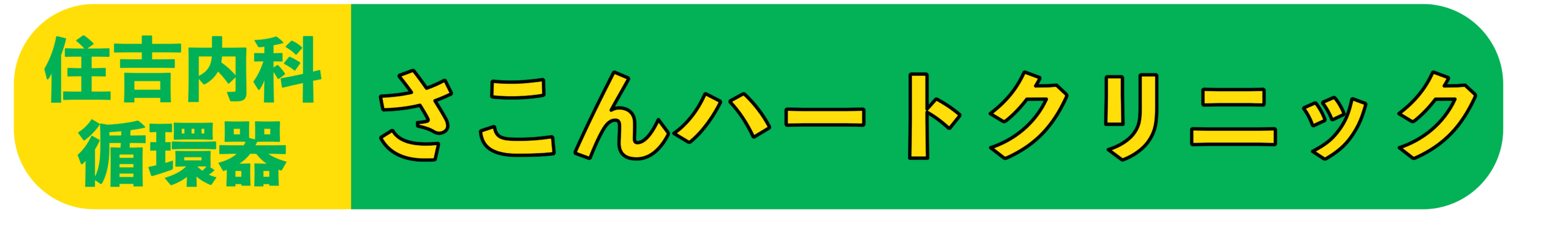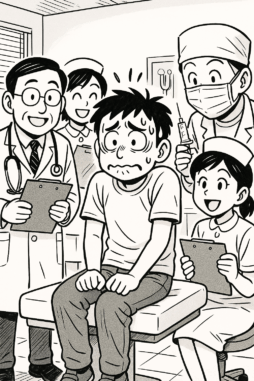意外な高血圧の原因「二次性高血圧」
二次性高血圧とは?原因・症状・治療法を循環器専門医がわかりやすく解説
高血圧と診断された方の中には、「なぜ自分が高血圧になったのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
また、「血圧の薬を飲んでいるのに、なかなか血圧が下がらない」、「中高年の病気と思っていたのに、若い時から血圧が高かった」という人もいるのではないでしょうか?
今回の内容は、その疑問を解決するヒントになると思いますので、思い当たる方は是非最後までお読みいただければ幸いです!!
実は、高血圧には大きく分けて2つの種類があります。
一つは「本態性高血圧」と呼ばれるもので、明確な原因がわからないタイプです。高血圧患者さんの約90%がこちらに該当します。
もう一つが「二次性高血圧」です。こちらは特定の病気や薬の影響によって血圧が上がってしまうタイプで、高血圧患者さんの約10%を占めています。
二次性高血圧の最大の特徴は、原因となっている病気を治療することで高血圧が改善する可能性が高いということです。つまり、「治りやすい高血圧」と言えるでしょう。
今回は、循環器専門医として二次性高血圧の病態について、皆さんにわかりやすくお伝えしたいと思います。
【二次性高血圧の主な原因疾患】知っておきたい病気の種類
二次性高血圧を引き起こす病気は、実にさまざまです。代表的なものをご紹介しましょう。
腎臓の病気による高血圧
腎臓は血圧を調節する重要な臓器です。腎臓の機能が低下すると、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、血圧が上昇します。
「腎実質性高血圧」は、慢性腎炎や糖尿病性腎症などの腎臓病によって起こります。腎臓の組織が傷つくことで、血圧を下げるホルモンの分泌が減少し、結果として高血圧になってしまいます。
「腎血管性高血圧」は、腎臓に血液を送る動脈が狭くなることで発症します。動脈硬化や繊維筋性異形成という病気が原因となることが多いです。
腎臓が「血液が足りない」と誤解して、血圧を上げるホルモン(レニン)を過剰に分泌してしまうのです。
ホルモンの異常による高血圧
私たちの体には、血圧を調節するさまざまなホルモンがあります。これらのホルモンのバランスが崩れると、高血圧が起こります。
「原発性アルドステロン症」は、副腎という臓器からアルドステロンというホルモンが過剰に分泌される病気です。このホルモンは体内にナトリウム(塩分)を溜め込む働きがあるため、血圧が上昇します。
「褐色細胞腫」では、アドレナリンやノルアドレナリンという興奮作用のあるホルモンが過剰に分泌されます。これらのホルモンは心臓の拍動を強くし、血管を収縮させるため、血圧が急激に上昇することがあります。
「クッシング症候群」は、コルチゾールというステロイドホルモンが過剰になる病気です。このホルモンも血圧を上昇させる作用があります。
「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」も見逃せない原因の一つです。甲状腺は首の前側にある蝶々のような形をした臓器で、体の新陳代謝を調節するホルモンを分泌しています。
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、心臓の拍動が速くなり、収縮する力も強くなります。また、血管の抵抗も変化するため、特に収縮期血圧(上の血圧)が上昇しやすくなります。
その他の原因
「睡眠時無呼吸症候群」も二次性高血圧の重要な原因の一つです。睡眠中に呼吸が止まることで、体が酸素不足を感じ、交感神経が活発になって血圧が上昇します。
また、一部の薬剤も高血圧の原因となることがあります。非ステロイド系消炎鎮痛薬(NSAIDs)や経口避妊薬、漢方薬の甘草などが該当します。
【二次性高血圧の症状と診断】早期発見のポイント
二次性高血圧を早期に発見することは、効果的な治療につながる重要なステップです。どのような症状や特徴があるのでしょうか。
注意すべき症状
二次性高血圧では、通常の高血圧とは異なる特徴的な症状が現れることがあります。
若い年齢(30歳未満)で高血圧が発症した場合や、急に血圧が高くなった場合は要注意です。また、血圧が非常に高い値を示す場合(収縮期血圧180mmHg以上、拡張期血圧110mmHg以上)も二次性高血圧の可能性があります。
原発性アルドステロン症では、筋力低下やこむら返り、多尿などの症状が見られることがあります。これは血液中のカリウムが低下するためです。
褐色細胞腫では、頭痛、動悸、発汗、顔面蒼白などの症状が発作的に現れることが特徴的です。まるでパニック発作のような症状が起こることもあります。
甲状腺機能亢進症では、動悸、息切れ、手の震え、体重減少、暑がり、イライラなどの症状が見られます。また外見上も、眼球が突出したり、首の腫れ(甲状腺腫)が見られたりすることもあります。これらの症状は徐々に現れることが多いため、気づきにくいことも多いです。
睡眠時無呼吸症候群では、大きないびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛などが見られます。
診断の進め方
二次性高血圧が疑われる場合、医師はさまざまな検査を行います。
まず基本的な血液検査で、腎機能やホルモンの値を調べます。特に、レニン、アルドステロン、コルチゾール、甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)などの測定が重要です。
画像検査では、腹部CT検査やMRI検査により、副腎や腎臓の状態を詳しく調べます。腎血管性高血圧が疑われる場合は、造影剤を使った血管撮影検査を行うこともあります。
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、睡眠ポリグラフという睡眠中の無呼吸を検出する検査を行います。
これらの検査により、二次性高血圧の原因を特定し、適切な治療方針を決定します。
【二次性高血圧の治療法】原因に応じた効果的なアプローチ
二次性高血圧の治療は、原因となっている病気を治療することが基本となります。これが本態性高血圧との大きな違いです。
腎臓病による高血圧の治療
腎実質性高血圧の場合、まず腎臓病の進行を抑える治療を行います。ACE阻害薬やARBという種類の降圧薬は、腎臓を保護する効果があるため、第一選択として使用されます。
また、食事療法も重要です。塩分制限(1日6g未満)とタンパク質制限により、腎臓への負担を軽減します。
腎血管性高血圧では、狭くなった血管を広げる治療を行います。カテーテルを使って血管内にステントという器具を留置する「経皮的腎動脈形成術」や、外科手術による血管再建術が選択されます。
ホルモン異常による高血圧の治療
原発性アルドステロン症では、副腎の腫瘍が原因の場合は外科手術により腫瘍を摘出します。両側の副腎に問題がある場合は、スピロノラクトンという薬でアルドステロンの作用を阻害します。
褐色細胞腫も基本的には外科手術による摘出が治療の中心となります。手術前には、アドレナリンの作用を抑える薬(αブロッカー、βブロッカー)を使用して、血圧や心拍数を安定させます。
クッシング症候群では、原因に応じて下垂体や副腎の手術、薬物療法などを行います。
甲状腺機能亢進症の治療では、抗甲状腺薬により甲状腺ホルモンの産生を抑制します。薬物療法で改善しない場合や再発を繰り返す場合は、放射性ヨウ素治療や甲状腺摘出手術を検討することもあります。
その他の治療
睡眠時無呼吸症候群では、CPAP(持続陽圧呼吸療法)という治療法が効果的です。睡眠中にマスクを装着し、持続的に空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぎます。
また、減量や禁酒、禁煙なども重要な治療の一部となります。
薬剤性高血圧の場合は、原因となっている薬の中止や変更を検討します。ただし、必要な薬の場合は、医師と相談の上で代替薬への変更を行います。
治療効果と予後
二次性高血圧の治療効果は、原因疾患や発見時期によって異なりますが、多くの場合で良好な結果が期待できるため、血圧の正常化や著明な改善が得られることが多く、降圧薬の減量や中止が可能になることもあります。
ただし、腎臓病が進行している場合や、高血圧の持続期間が長い場合は、完全な正常化は困難なこともあります。それでも、進行を遅らせることは十分可能です。
まとめ
二次性高血圧は、原因となる病気を治療することで改善が期待できる「治りやすい高血圧」です。
早期発見・早期治療が何より重要であり、適切な診断と治療により、多くの患者さんで良好な治療効果が期待できます。
高血圧と診断された方、特に若年発症や急激な血圧上昇、特徴的な症状がある方は、ぜひ当院にご相談ください。
二次性高血圧かもしれないと心配している方も、まずは受診し、適切な検査を受けることをお勧めします。
正しい診断と治療により、健康で質の高い生活を送ることができるはずです!!